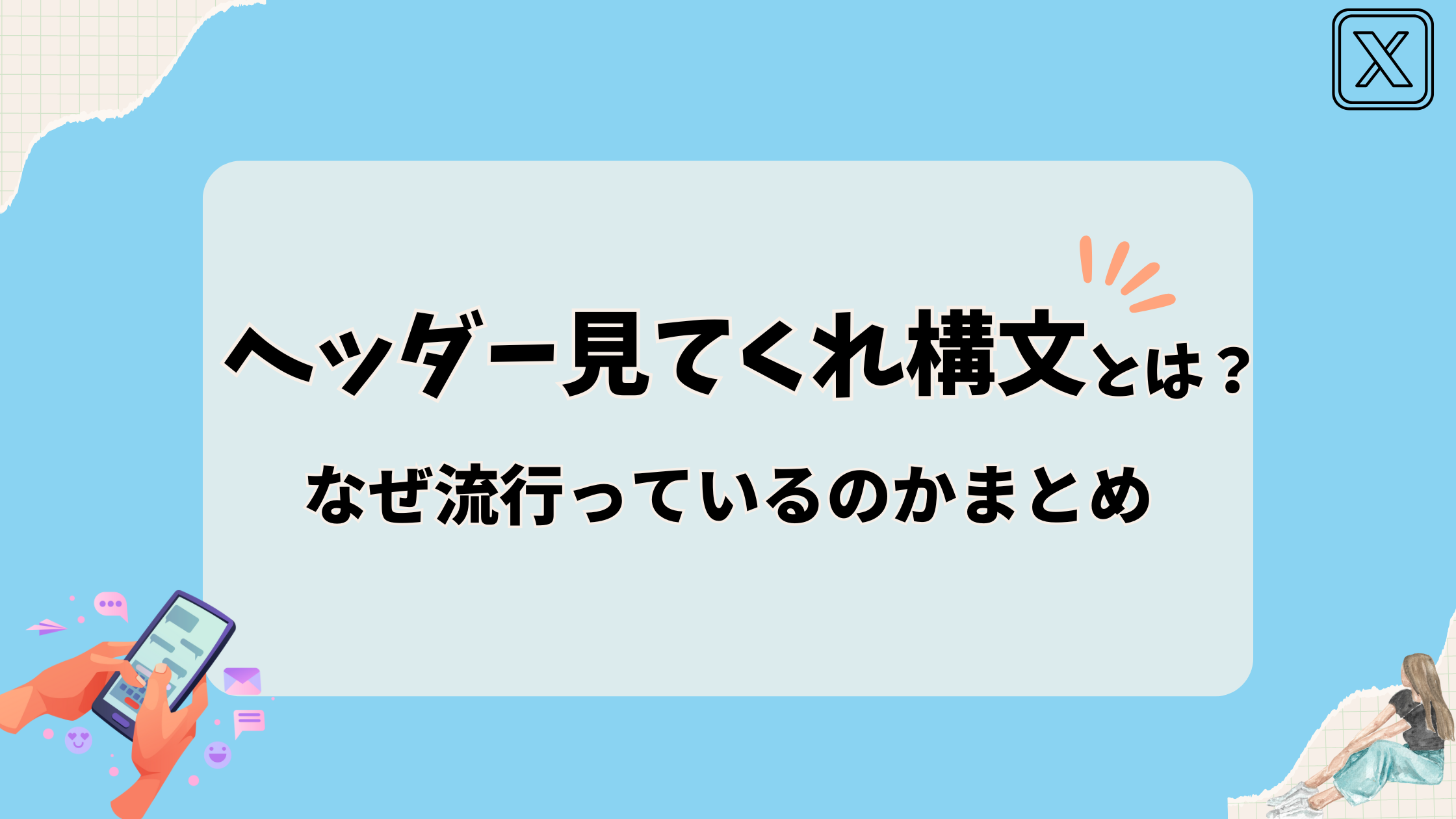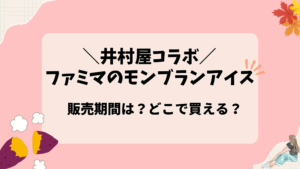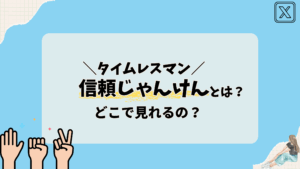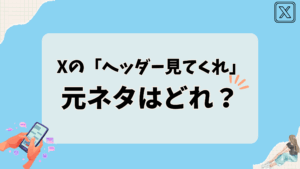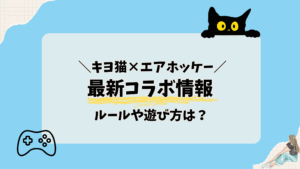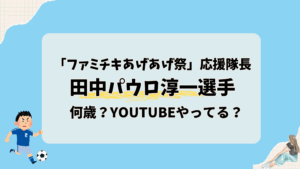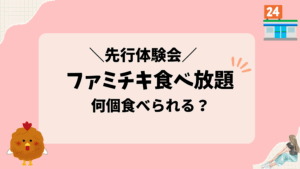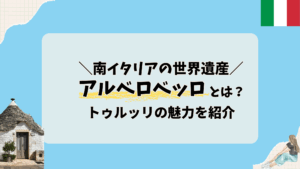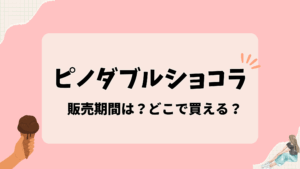「最近Xのタイムラインで『ヘッダー見てくれ構文』をよく見るけど、結局何のこと?」と気になっていませんか?
突然流行りだしたネットスラングは、元ネタを知らないと置いてけぼり感がありますよね。
この記事では、ヘッダー見てくれ構文の意味や流行のきっかけ、そして楽しみ方までわかりやすく解説します。
読み終わるころには、きっと話題に乗れるはずですよ!
ヘッダー見てくれ構文とは?基本の意味を解説

最近X(旧Twitter)で急速に広がっている「ヘッダー見てくれ構文」。タイムラインでも頻繁に目にするようになり、「結局これは何?」と疑問を持つ人が増えています。
ヘッダー見てくれ構文は、プロフィールページのヘッダー画像を題材にした大喜利的な投稿スタイルです。
ヘッダー見てくれ構文の具体的な例
基本構造はとてもシンプル。
- 1枚目の投稿で「Xのヘッダーに画像が収まらない」と悩みを表現
- 2枚目で「うまくいった!ヘッダー見てくれ」と仕上がりを見せる
この流れでスクショや写真を組み合わせ、笑いを取ったり、ネタを披露する遊びとして広まっています。
ヘッダー見てくれ構文と従来の違い
これまで流行してきた「大喜利系ミーム」はテキスト単体が多めでした。対してヘッダー見てくれ構文は プロフィールのヘッダー画像 というX特有の機能を活用しているのが特徴です。
そのため、自然と「プロフィールを見に来てもらう効果」もあり、ネタと自己アピールが一体化している点が新しいと言えるでしょう。
なぜヘッダー見てくれ構文が流行っているのか?

流行の背景にあるSNSやミーム文化
2025年9月16日深夜ごろから急速に広まったとされるこの構文。
きっかけは海外ユーザーの投稿ではないかと推測されます。
「うまくいったわ、ヘッダー見てくれ」というミームの元ネタは、保守系活動家チャーリー・カークの写真を利用した風刺的な投稿とされています。
Nvm I figured it out https://t.co/U24dNOOD42
— ɹoʇɐʇoɹ pɹoʍ (@wrotator) September 14, 2025
最初のツイートで「画像がヘッダーに収まらない」とあえて釣りを行い、次の投稿で「うまくいった」とユーザーを誘導。
その流れでプロフィールのヘッダーを見ると、棺桶に入ったカークの姿が表示される仕掛けになっていました。
「収まらない→棺桶に収まった」という皮肉な構造が元ネタだったのです。
元ネタを知らずに使っていると、皮肉な投稿になってしまうかも…
開発者やデザイナーの間での使われ方
単なる大喜利だけでなく、プロフィールへの導線を自然に作れるため、マーケティング的にも応用できると注目されています。
 アー子
アー子実際に私も深夜に「ヘッダー見てくれ」の一文でいろんなアカウントのプロフィールを見てしましました。
まとめ:ヘッダー見てくれ構文の魅力と注意点


ヘッダー見てくれ構文は、Xで2025年9月に誕生した最新のミームです。
まとめ
- 基本は「ヘッダー収まらない → できた! → 見てくれ」の流れ
- 大喜利として笑いを誘う一方、プロフィールへの導線効果もある
- シンプルで参加しやすく、多くのユーザーが乗っかりやすい
注意点としては、あくまで流行の一過性が強い点です。数日から数週間で落ち着く可能性が高く、使いすぎると「今さら感」が出てしまうかもしれません。
ただし、このような流行りの構文はネット文化を知るうえで格好の題材。話題に触れることで、フォロワーとの距離を縮めたり会話のきっかけを作ることができます。